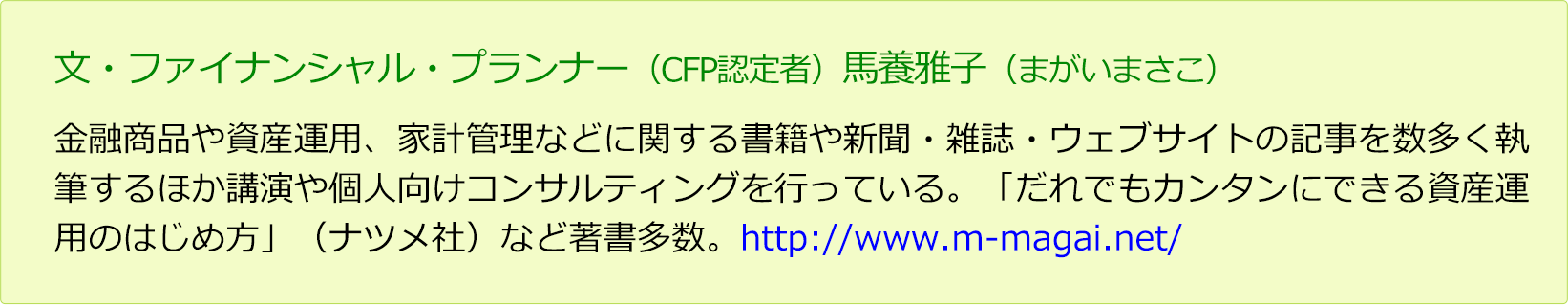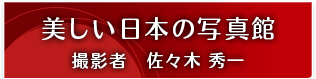08 知っておきたいシニアのマネー 医療と介護に備える
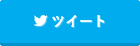
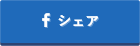
08-01 老後の医療費はいくら
(1)自己負担は最大3割
年齢を重ねると、どんなに健康に気をつけていても体のどこかに不具合が生じてきて、病院に通ったり入院したりする回数が多くなりがちです。そのため、老後に病気やケガで医療費がかさみ、老後資金が不足することを心配する人も多いのではないでしょうか。
でも、日本の公的医療制度は先進国の中でも非常に手厚く、医療費の自己負担額は抑えられています。ここでは公的医療保険の仕組みを見ていきましょう。
日本ではすべての人が、何らかの公的な医療保険に加入することになっています。公的医療保険に加入している人や、その人に扶養されている家族が医療機関で治療を受けたとき、かかった医療費の一部を負担すればすみます。その負担割合は年齢や所得によって次のようになっています。
このように、どんなに医療費がかかっても、自己負担は最大3割で、75歳以上になると多くの人は1割負担になるわけです。
■医療費の自己負担割合
でも、日本の公的医療制度は先進国の中でも非常に手厚く、医療費の自己負担額は抑えられています。ここでは公的医療保険の仕組みを見ていきましょう。
日本ではすべての人が、何らかの公的な医療保険に加入することになっています。公的医療保険に加入している人や、その人に扶養されている家族が医療機関で治療を受けたとき、かかった医療費の一部を負担すればすみます。その負担割合は年齢や所得によって次のようになっています。
このように、どんなに医療費がかかっても、自己負担は最大3割で、75歳以上になると多くの人は1割負担になるわけです。
■医療費の自己負担割合
・69歳まで
| 自己負担割合 | 小学校入学まで | 2割 |
| 小学校入学から69歳まで | 3割 |
・70~74歳
| 自己負担割合 | |
| 一般 | 2割 |
| 現役並み所得者 | 3割 |
・75歳以上
| 自己負担割合 | |
| 一般 | 1割 |
| 現役並み所得者 | 3割 |
*現役並み所得者のめやす:1人暮らしで年収383万円以上、2人世帯で年収520万円以上
このように、どんなに医療費がかかっても、自己負担は最大3割で、75歳以上になると多くの人は1割負担になるわけです。
(2)自己負担には上限が
「3割負担だったとしても、医療費が100万円かかったら30万円支払うことになる」と思うかもしれませんが、そうではありません。1カ月の自己負担額には上限が設けられていて、それを超えた分は「高額療養費」として払い戻される仕組みがあるのです。どんなに医療費がかかっても、自己負担額は一定額までというわけです。
自己負担の上限額は年齢と所得によって次のようになっています。
■医療費の自己負担限度額(A=かかった医療費の総額)
自己負担の上限額は年齢と所得によって次のようになっています。
■医療費の自己負担限度額(A=かかった医療費の総額)
・69歳まで
| 年収区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数回該当の場合 |
| 約1,160万円~ | 252,600円+(A-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 約770万円~1,160万円 | 167,400円+(A-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 約370万円~約770万円 | 80,100円+(A-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 約370万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税者等 | 35,400円 | 24,600円 |
・70歳以上(2018年8月診療分から)
| 区分 | 自己負担限度額 | ||
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
| 現役並み | 年収約1,160万円~ | 252,600円+(A-842,000円)×1% | |
| 年収約770万円~1,160万円 | 167,400円+(A-558,000円)×1% | ||
| 年収約370万円~約770万円 | 80,100円+(A-267,000円)×1% | ||
| 一般 | 年収156万円~約370万円 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 | ||
例えば、70歳未満で年収370~770万円の会社員の場合、1カ月に医療費が100万円かかったとしても、自己負担額は
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
となります。医療機関の窓口でいったん3割負担分の30万円を支払いますが、上限額である87,430円を超えた部分(212,570円)はあとから払い戻しが受けられます。
さらに、同じ世帯で12カ月間に3カ月以上、医療費が限度額に達して高額療養費の払い戻しを受けた場合は「多数回該当」となり、4カ月目以降は自己負担額がさらに下がります。
70歳以上の場合、例えば夫が入院し妻が通院しているといったケースでは、かかった医療費を世帯で合算することができ、それに対して上限額が決められています。
加入している健康保険組合によっては上限額がこれより低い場合があります。また、住んでいる自治体が独自の医療費助成制度を設けていることもあります。
このように、医療費については自己負担が重くならないような仕組みが設けられているので、「医療費で破産」といったことは基本的にはないと考えてよいでしょう。
(3)医療費の払い戻し
医療費の1カ月の自己負担上限額は年収で細かく分かれていますが、これを自分で計算する必要はありません。医療機関の窓口で1~3割の自己負担額を支払ったあと、加入している公的医療保険(健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の窓口に高額療養費の支給申請書を提出すると、おおむね3カ月後くらいに払い戻しが受けられます。
健康保険組合の中には、こうした手続きをしなくても、自動的に払い戻しをしてくれるところもあります。
払い戻しを受けるまでは患者が医療費を立て替える形になりますが、69歳までの人は事前に加入している公的医療保険の窓口で「限度額適用認定証」を発行してもらい、それを健康保険証とともに医療機関に提出すると、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなり、医療費を立て替えなくてすみます。
また、70歳以上の人は医療機関を受診するときに健康保険証と高齢受給者証を提出すれば、高額療養費の申請手続きは不要です。
健康保険組合の中には、こうした手続きをしなくても、自動的に払い戻しをしてくれるところもあります。
払い戻しを受けるまでは患者が医療費を立て替える形になりますが、69歳までの人は事前に加入している公的医療保険の窓口で「限度額適用認定証」を発行してもらい、それを健康保険証とともに医療機関に提出すると、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなり、医療費を立て替えなくてすみます。
また、70歳以上の人は医療機関を受診するときに健康保険証と高齢受給者証を提出すれば、高額療養費の申請手続きは不要です。
(4)医療費以外の負担も
医療費の自己負担額に上限があることを知っていれば、費用の心配なく医療機関を受診でき、老後の医療費の不安もやわらぐでしょう。ただし、注意点もあります。
医療費自己負担の上限額がだんだんに引き上げられてきています。今後も引き上げがあるかもしれません。
また、医療費の自己負担割合も上限額も、健康保険の対象、いわゆる「保険がきく」医療にかかる費用に対して適用されます。それ以外のものにかかる費用は全額自己負担となります。
公的保険の対象でないものには、
・先進医療など、健康保険が適用されない治療にかかる費用
・入院時の食事代:1食当たり460円(2018年4月~)
・差額ベッド代(患者が希望して利用した場合)
・入院時に必要な日用品、テレビ代、本・雑誌代など
・通院にかかる交通費
などがあります。
こうした費用負担に備えるには、民間保険会社の医療保険に加入するか、貯蓄の一部を医療費用として取り分けておくことが考えられます。
医療費自己負担の上限額がだんだんに引き上げられてきています。今後も引き上げがあるかもしれません。
また、医療費の自己負担割合も上限額も、健康保険の対象、いわゆる「保険がきく」医療にかかる費用に対して適用されます。それ以外のものにかかる費用は全額自己負担となります。
公的保険の対象でないものには、
・先進医療など、健康保険が適用されない治療にかかる費用
・入院時の食事代:1食当たり460円(2018年4月~)
・差額ベッド代(患者が希望して利用した場合)
・入院時に必要な日用品、テレビ代、本・雑誌代など
・通院にかかる交通費
などがあります。
こうした費用負担に備えるには、民間保険会社の医療保険に加入するか、貯蓄の一部を医療費用として取り分けておくことが考えられます。